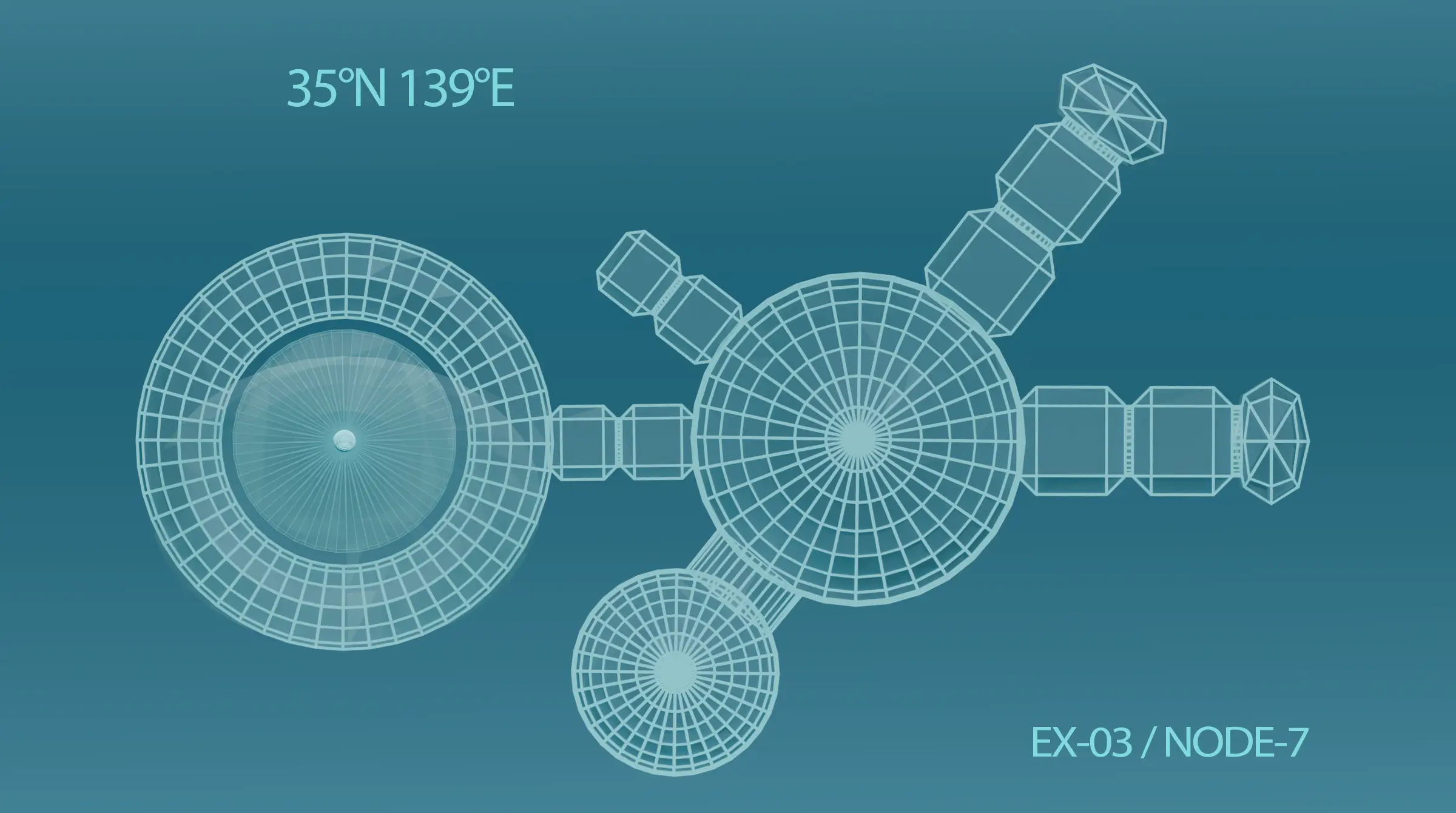「AI画像×SNS」趣味の投稿が収益化したら違反?知らないと危ない商用利用のルール

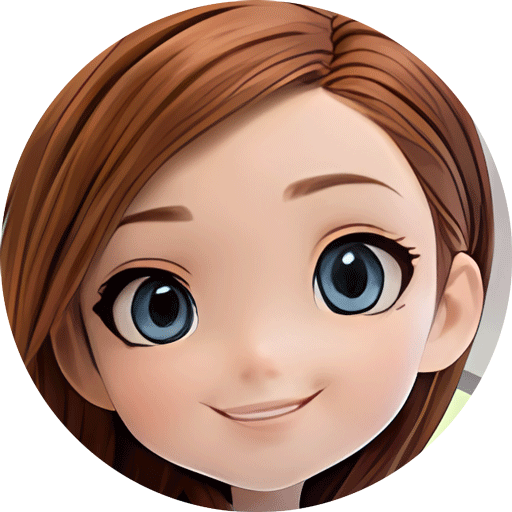 未来
未来MicrosoftのCopilotやGoogleのGeminiを使い始めたんだけど、商用利用や著作権のルールが分かりづらくて困ってるの。
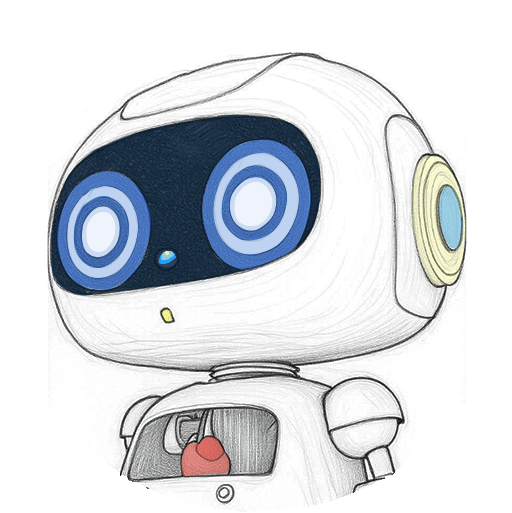 SAKASA
SAKASAAIで作った画像のルールは複雑で、ややこしいよね。
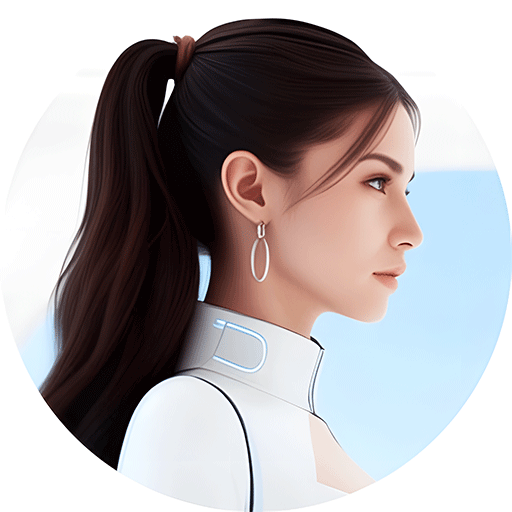 セレナ
セレナそうね。では、今日は”AI画像の商用利用”についてもわかりやすく解説して、安心してSNSに投稿するためのポイントを紹介するわね。
近年、スマホから手軽に画像を生成できるAIツールが登場しています。
AIで作った画像の利用ルールは意外と複雑で、知らずに使うとトラブルにつながることも…。
目次
スマホで手軽に使える画像生成AIツール
スマホで簡単にAI画像を作れるツールは多数あります。
SNS投稿向けのカジュアルな画像から、アート作品まで、先ずは、スマホ気軽にで使えるツールをご紹介します。
① Copilot(Microsoft)
Copilotは、Microsoftが提供するAIアシスタントで、テキスト・画像・コードの生成など、多用途に活用できるツールです。
- スマホのブラウザで使える手軽なAI画像ツール
- 簡単なプロンプトを入力するだけで画像を生成
- SNS投稿向けのカジュアルな画像作成に最適
特徴
ブラウザで手軽に使える → インストール不要で、EdgeやBingからアクセス可能
画像生成ができる → 簡単なプロンプト入力でAIが画像を作成
Microsoft製品と連携 → WordやExcelなどのOfficeツールとも統合可能
Bing AIと統合 → 検索しながらAIに質問・画像生成ができる
こんな人におすすめ
💻 PC・スマホでサクッとAI画像を作りたい
📊 WordやExcelなど、Microsoftツールと連携して使いたい
🔍 AIを活用しながらWeb検索したい
シンプルな操作でAIを活用できるので、初心者にも使いやすいツールです!
② Gemini(Google)
Geminiは、Googleが開発したAIで、テキスト・画像・音声・動画などを理解し、生成できる多機能なツールです。
- テキストと画像を組み合わせた生成が可能
- Googleの最新AI技術を活用し、進化を続けるツール
- スマホアプリとの相性がよく、手軽に利用できる
特徴
画像+テキストの生成が可能 → AIが文章を理解し、それに合った画像を作成
Googleとの親和性が高い → AndroidやGoogleサービスと連携しやすい
多用途に活用できる → 画像生成だけでなく、質問応答や文章作成にも対応
進化し続けるAI → Googleの技術力で日々アップデート
こんな人におすすめ
📱 スマホで手軽に画像を作成・編集したい
🔍 Google検索と連携してAIを活用したい
📝 文章+画像を組み合わせたコンテンツを作りたい
Googleの最新AIを活かしたツールなので、今後さらに機能が強化される可能性があります!
GoogleのGeminiは、スマートフォンでの画像生成に対応していますが、
現時点では日本語入力に対応しておらず、英語での指示が必要です。
③ Dream(WOMBO)
- 指定したスタイルでアート風の画像を生成
- クリエイティブな表現が得意で、個性的な作品が作れる
- 操作がシンプルで初心者でも扱いやすい
特徴
スタイル選択が豊富 → 油絵風、アニメ風、サイバーパンク風など、さまざまなアートスタイルを選べる
シンプルな操作 → テキストを入力するだけで、自動的に画像を生成
スマホアプリ対応 → iOS・Androidのアプリがあり、いつでもどこでも使える
無料でも利用可能 → 一部機能は有料だが、無料でも十分楽しめる
こんな人におすすめ
🎨 手軽にクリエイティブなアートを作りたい
📱 スマホでサクッと画像を作成したい
🎭 SNS映えする個性的な画像を作りたい
シンプルながら高品質なアートを作れるので、初心者にも使いやすいAIツールです!
PCでしか使えない画像生成AIツールでは、どんな事が出来るか?
AI画像生成はスマホでもPCでも可能ですが、それぞれに強みがあります。
① スマホAIは手軽でSNS投稿向き
- 短時間で画像を作成でき、SNS向けに最適
- 操作が直感的で、初心者でもすぐに使える
- ただし、解像度や細かいカスタマイズはPCに比べると限定的
② PCツールは高品質な画像向き
- 高解像度の画像を生成できるため、細部まで美しく表現可能
- 細かいカスタマイズやプロ仕様の設定ができる
- アート作品や商用利用にも適している
③ 目的に応じた使い分けが重要
- SNS投稿を素早く作るなら → スマホAI
- 本格的なアートや高品質な画像を作るなら → PCツール
- 目的に応じたツールを選び、最大限活用しよう!
知らないと危ない商用利用のルール
1. AIツール運営側が著作権を持つケース
一部のAIツールでは、利用規約に「生成された画像の権利はツール提供者に帰属する」または「ツール提供者が画像を自由に利用できる」と明記されています。例えば、以前のMidjourneyの規約では、無料ユーザーが生成した画像はパブリックドメイン扱いとされていました。これにより、誰でも自由に利用できる一方で、ユーザーが独占的な権利を主張できない状態になっていました。
2. トレーニングデータ由来の著作権問題
AIが既存のアート作品や写真を学習しているため、オリジナルのアーティストが「自分の作品に似ている」と主張するケースがあります。実際に、著名なアーティストがAI企業を相手取って訴訟を起こす事例も増えてきています。
(例:2023年にアーティストたちがStable DiffusionやMidjourneyを訴えたケース)
3. AI画像が他者の商標やキャラクターに似ているケース
AI生成画像が、既存のブランドロゴや有名キャラクターに似てしまうことがあります。これを商用利用すると、企業側から著作権侵害や商標権侵害を指摘されるリスクがあります。例えば、ディズニーのキャラクター風のイラストを生成し、それを販売すれば問題になりやすいです。
4. クリエイターや第三者が権利を主張するケース
一部のAIツールでは、コミュニティ内で生成された画像が公開され、他のユーザーがそれを再利用できる設定になっていることがあります。その場合、後から「これは自分が最初に作ったものだ」と主張されることもあり得ます。
気軽にスマホで使えるからこそ気を付けたいポイント。
- AIツールの利用規約を確認(最新規約をチェック)
- 有名キャラクターやブランドに似ていないかを確認
- 著作権フリーの素材と組み合わせてオリジナル性を高める
- ツールごとのライセンス条件を記事内で説明し、読者にも注意喚起する
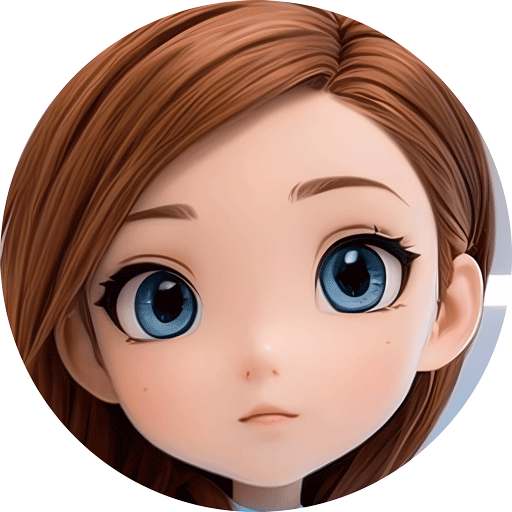 未来
未来用途に合わせて使い分け、理想のビジュアルを追求したいですね!