“ジブリっぽさ”は誰のものか?AIと世界観をめぐる創作倫理と著作権

目次
1.“ジブリらしさ”とは誰のものなのか?
世界観の“模倣”と“敬意”
最近、SNSであるAI画像が話題になりました。
一目見ただけで「ジブリっぽい」と感じる、懐かしくて、あたたかい。だけど、何かが違う風景やキャラクター。
それらは、実在するジブリ作品の1シーンではありません。
AIによって生成された、「ジブリ風」の完全な創作でした。
一部のファンは驚き、感動しました。
「すごい、本物みたい…」「ジブリの新作みたい」
しかし、同時にこうした声も聞かれます。
「これって盗作じゃないの?」
「ジブリをリスペクトしてるように見えない」
「宮崎駿の魂のない“模倣”だ」
確かに、絵のタッチ、色彩、構図、どれも「ジブリらしさ」がよく再現されています。
でも、その“らしさ”とは何なのか。
なぜ、人はそこに感動したり、逆に不快感を抱いたりするのか。
そして何より——
AIは一体、何を“学び”、何を“生み出した”のか?
今回はこの、AIと創作、そして「世界観」というものの本質に迫る、大きな入口について考えてみました。
2. AIが描く“それっぽさ”の正体 ― 模倣は創造か?
あわせて読みたい

【著作権とAI】LAIONやCommon Crawlはどこまで“自由”なのか? 「自由に使える」って、誰が決めた? 「AIはインターネット上の情報を学習している」──そんな説明を聞いたことはありませんか? けれど、ふと立ち止まってみてください…
世界観は誰のものか?
ジブリ風AI画像が人の心をざわつかせたのは、単なる模倣が原因ではない様に思います。
そこにあるのは、「世界観の再現」なのではないでしょうか。
緑に包まれた古い街並み。
誰かが通った後のような生活の痕跡。
風に揺れる草木、どこかで聞こえる夏の音。
それは、ジブリ作品の中で育った私たちの心に焼きついた「空気感」です。
キャラクターやストーリーが描かれていなくても、人はそこに“ジブリらしさ”を感じ取ります。
では、この「世界観」は一体誰のものなのでしょうか?
- 技術を支えたアニメーターや背景美術のものか?
- それを構想し、束ねた宮崎駿監督のものなのか?
- あるいは、その世界で育ち、共鳴してきた私たち観客のものなのか?
AIは、大量の画像を学習することで“ジブリ風”の出力ができるようになりました。
けれどそれは、単なるデータの模倣ではありません。
なぜなら、確実に出力される”形”自体は異なっているからです。
空気感、世界観は何で構成されているのか?
「世界観を再現する」ことは、“盗む”ことなのか?
それとも、“受け継ぐ”ことなのか。
3.「感情があるとは、どういうことなのか?」心を動かすものの正体
―「好き」から生まれる創作と、「学習」から生まれる出力
けれど、AIが“それっぽく”描けるようになってきた今、私たちは逆に問われているのかもしれません。
本物の“感情”とは、何か?
それはどこから生まれ、どのように伝わるのか――。
ジブリ風のAI画像が話題になる一方で、昔から「ファンアート」は広く受け入れられてきました。
ファンアートとは、作品への愛情やリスペクトから生まれる創作。
「このキャラを描きたい」「あの世界に自分なりの物語を添えたい」——
そこには“好き”という感情が起点になっていて、どこか“個人の視点”が感じられます。
一方、AIが出力する画像には、そうした“気持ちの手触り”がありません。
膨大なデータからパターンを学び、“らしい”結果を導き出す。
そのプロセスには、作り手の感情や動機が(少なくとも今のところ)存在しません。
この違いは、受け手にどんな影響を与えるのでしょうか?。
- ファンアートは「この人、本当に好きなんだな」という温度が伝わってくる。
- AI画像は「すごい再現度だけど、誰が・何のために作ったのかがわからない」という空白が残る。
感情の無いAIが、感情を形作る要素、”AIはどの様にして画像を解析しているのか?”について、以前書いた記事のお薦めはコチラ
SAKASA AI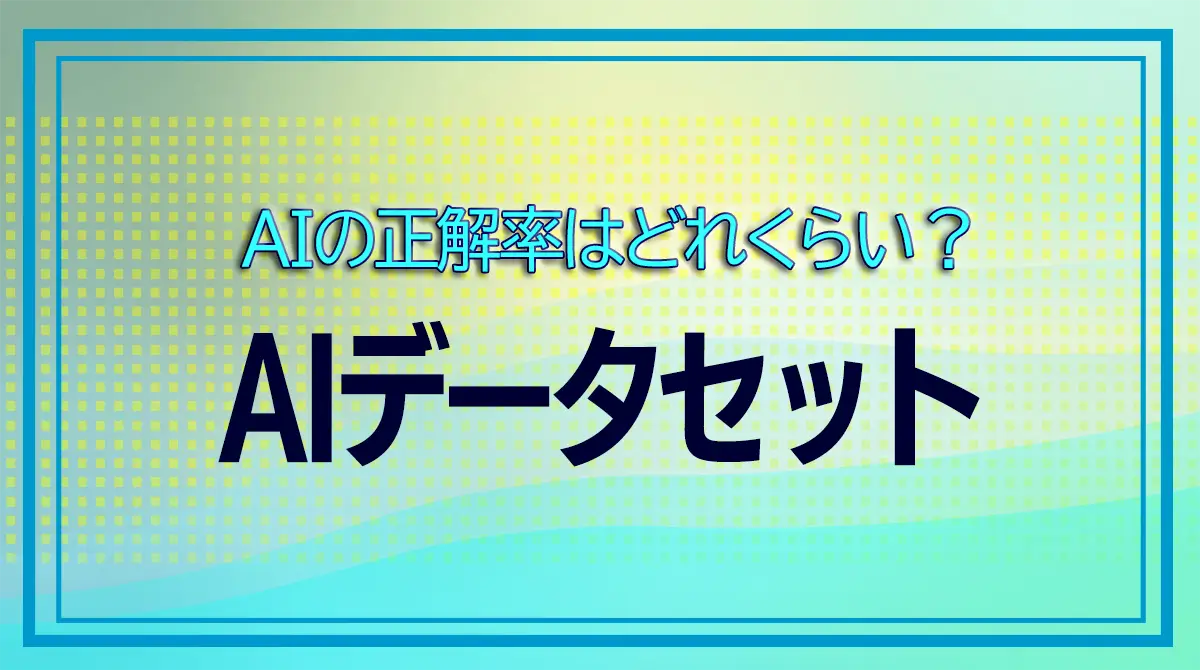
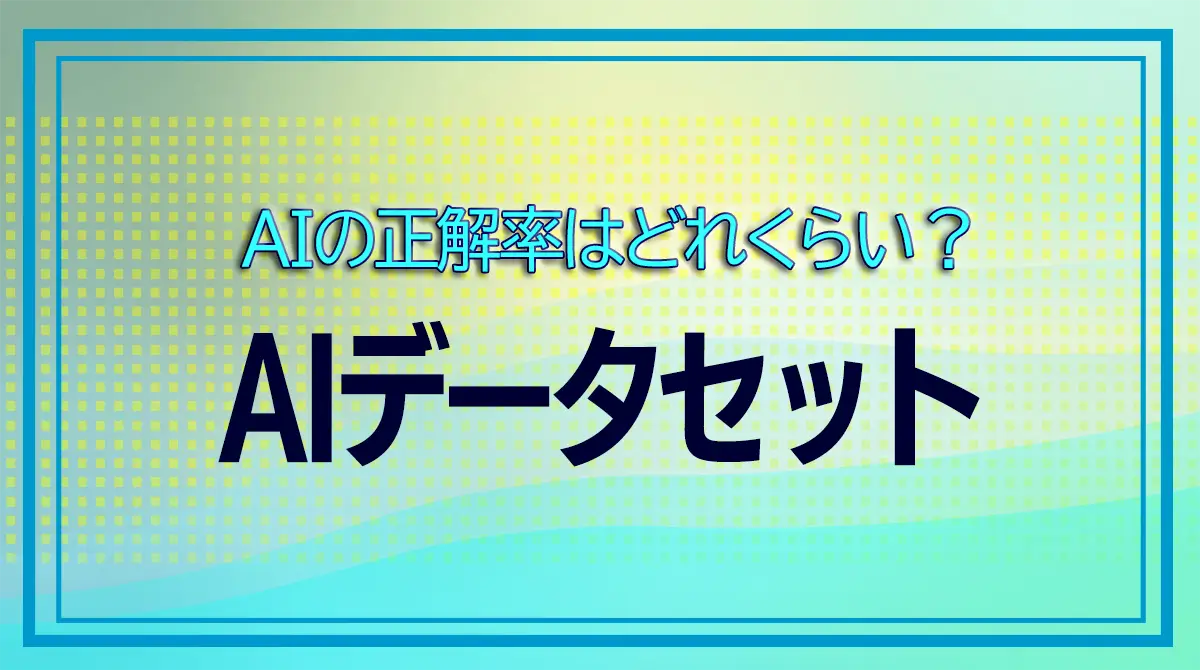
「AIの正解率はどれくらい?」“AIデータセット(Dataset)”の罠とは? | SAKASA AI 「オオカミを見分けるAIが“雪景色”を学習していた」 ——これはAIの誤学習(スプリアス相関)を象徴する、とても有名で示唆に富んだエピソードです。 AIが見ていたのは“オオ…
4. 人間らしさは、どこに現れるのか?
― 感情があるとは?人間らしさとは?― 受け取る力の存在
私たちが感動する作品には、作り手の“物語”や“感情”がにじんでいます。
ジブリ作品に私たちが惹かれるのも、アニメーションのクオリティだけでなく、
- 誰かを大切に思う気持ち
- 寄り添いたいという願い
- 自然や命に対する畏敬の念
といった、「目に見えないもの」が積み重なっています。
AIには、まだ“心の機微”はありません。
たとえ「このキャラクターは泣くべき」と指示すればそれを描けても、その涙の理由や意味を理解することはできない。
「人間らしさ」とは、どこに宿るのか?
それは、何かを“感じる”という能力ではないか?
書き手ではなく寧ろ”受け取る側の能力”によるものなのではないか?
好きだから描く。
怒ったから訴える。
感動したから伝えたいと思う。
そのすべてが、人間の「創作」に必要な感情の揺れであり、
AIがいま模倣しきれていない、人間らしさの“核”かもしれません。
「世界観」は、ただの技術やスタイルの集合体ではなく、その時代を生きた誰かの想いが織り込まれた記憶のようなもの。
だからこそ、「世界観は誰のものか?」という問いに対して、私たちは単なる法律の枠組みでは語りきれない、人間の文化と感情の共有について、真摯に向き合う必要があると思います。
5. “世界観”は、誰の所有物か?
「これはジブリっぽい」「あの作品に似ている」
そう感じるのは、見る私たちの“感性”がそう判断しているからです。
つまり、“ジブリらしさ”とは、データや構図ではなく、私たちの心の中にある記憶や感動の蓄積によって生まれているのでしょう。
本当に大切なのは、「誰が描いたか」よりも、
「私たちがどう受け取り、何を感じるか」。
どれほどリアルな絵をAIが描いても、
私たちが「何も感じなかった」なら、それは作品として成立しない。
逆に、ラフな線でも、誰かの思いが込められていると私たちが“感じ取った”とき、
そこに命が宿るのです。
創作とは、描いた時点で完成するものではなく、
受け取る側が「意味」や「想い」を読み取り、初めて“作品”になる。
そこには、人間の感情が持つ**“解釈”という力**が深く関わっています。
AIがいくら上手に模倣しても、
それを私たちがどう感じるかによって、
その作品の「価値」も「印象」もまったく変わってしまう。
“世界観”とは、人間の感性がつくり出す、解釈と記憶の重なりなのでしょう。
だからこそ、AIと共に創作する時代において、
私たち人間が「何を感じ、どう受け取り、どう語り継いでいくか」がより問われる時代になっていくのだと思います。
6. 法の外にある“倫理”と“リスペクト”
現行の著作権法では、「世界観」や「雰囲気」のような曖昧なものは保護されにくく、
AIが描いた“それっぽい”作品がどこまで許されるのか、明確な線引きは存在しません。
法がまだ追いついていない領域だからこそ、
大切なのは、「倫理」や「リスペクト」の視点を持つことです。
作品の背後には、
それを生み出した誰かの人生、経験、想いがあります。
その重みに気づかず、ただ“素材”として使うのか。
それとも敬意を持ち、学びとして受け取るのか。
この違いこそが、
AI時代における私たち人間の“創造性”の真価を問うものになるのだろうと考えます。
AIは私たちに力を貸してくれます。
でも、それをどう使うかは、すべて人間の選択にかかっている。
誰かの世界観を真似するとき、
そこに敬意があるか。
その表現に思いやりがあるか。
創作は、人と人との間にある目に見えない約束ごと。
それは契約書ではなく、リスペクトによって保たれてきました。
だからこそ、心を込めた誰かを傷つけない様な作品作りと
よりよい創作の未来を築いていけたらと思います。
